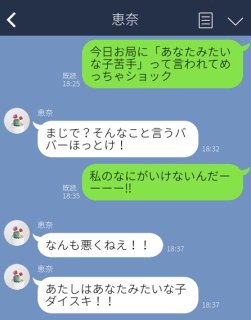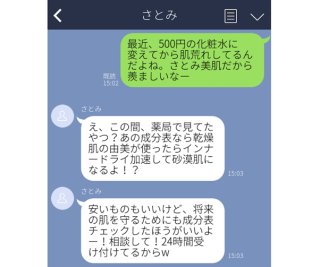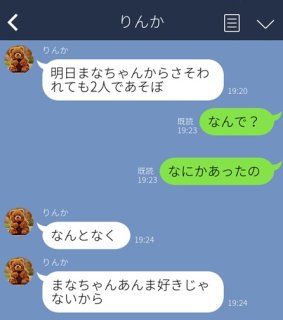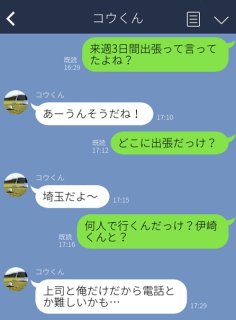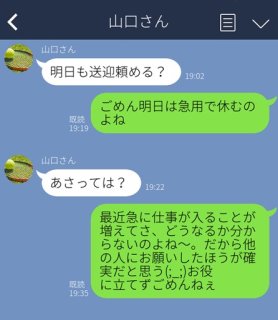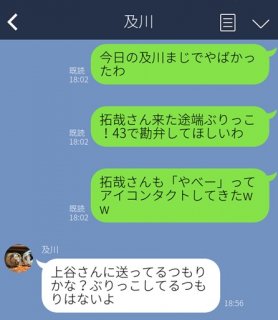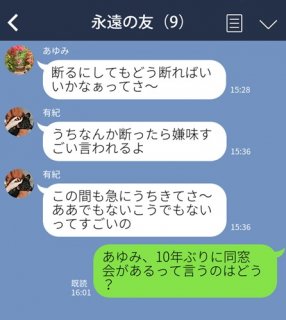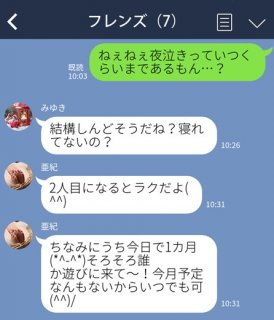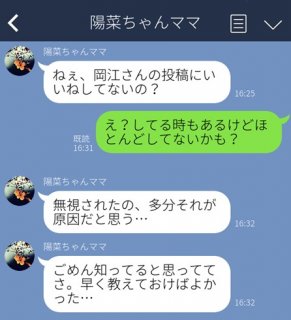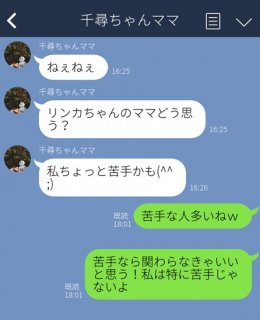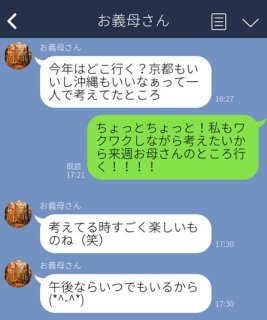客として現れたのは“松波のおっちゃん”
「おーい、いるかい」
ダミ声がメインフロアである客間に響く。朱里は、地元のお客さん第一号だと、ココロ弾ませ出迎えた。
「いらっしゃいませ!」
そこにいたのは、着古したよれよれポロシャツ姿の60代くらいの男性だった。
「おお、やっぱりあーちゃんいたよ」
想像との乖離に戸惑いながらも、“あーちゃん”という呼び名とその声は、記憶の奥底に確かにあった。
「…松波さん?」
「そうそう、松波のおっちゃんだよ! あんたのオヤジさんがさ、『娘がばあちゃんの家を改装して商売やる』って自慢してたからさ、覗いてみたわけ!!」
松波さんは響くような大声で笑った。彼は町の電機店の店主であり、町内会長である。朱里も小さい頃は家族ぐるみでお世話になっていた。
「食いもんやでもはじめたの?」
「え、あ、はあ」
「こりゃありがてぇや! なべさんのトンカツ屋も、勝又さんの喫茶店も閉めたばっかだしよ。行くとこなくて困ってたんだ!」
彼はそう叫んで、嵐のように去っていった。
「どうしたの? 顔、暗いけど」
客間に戻ってきた朱里の顔を萌絵は心配そうにのぞき込んだ。
「いや…」
松波さんは、人望厚い地元の名物おじさんだ。好意的に受け止めてくれたのは嬉しかった。
多少、嫌な予感を抱きながら、朱里は駐車場を出てゆく彼の軽トラックを勝手口の扉ごしに見送った。
おじさん達の溜まり場に
朱里のぼんやりとした不安は的中した。
「あーちゃん、水お代わり。カレーがさ、辛レーんだよ。なんつて」
松波さんは座敷にどでんと胡坐をかきながら、空のコップを差し出した。その横では、彼のお仲間たちが世間話に興じながら雑にカレーをかきこんでいる。
「もし、辛いのであればラッシーはいかがですか」
「サービスならもらうよ。700円ってなあ。ハハハハハ」
朱里は返事もせず微笑みだけ返してその場を去った。カレーを注文してくれるのはまだいい方だったから。
「あーちゃん、おかわりはもちろん無料だろ、な? おーい」
朱里は聞こえないふりをして、店の奥の厨房に逃げていく。
ライフスタイル 新着一覧




 公式X(Twitter)をフォロー
公式X(Twitter)をフォロー