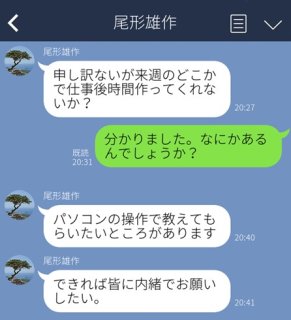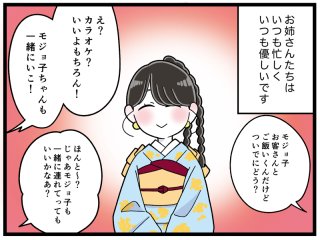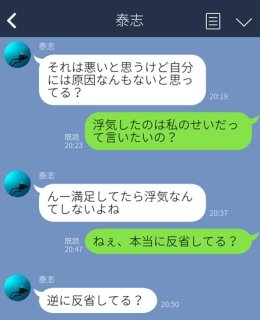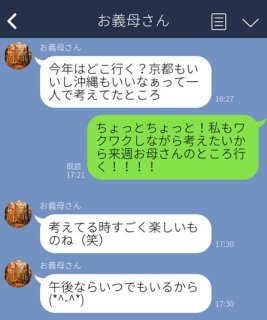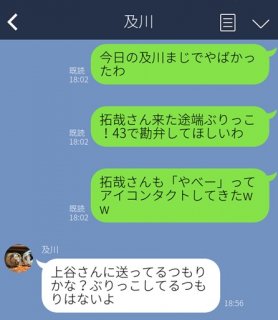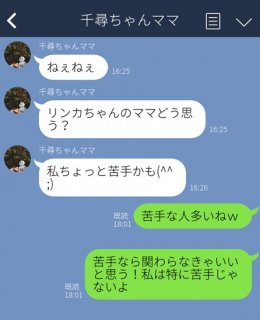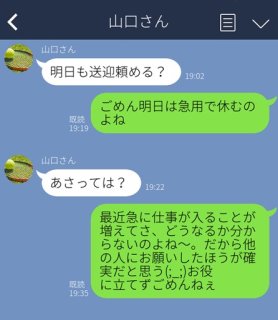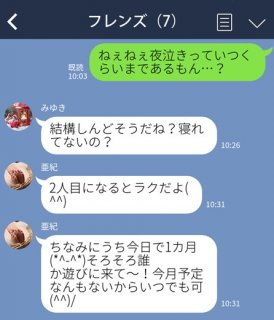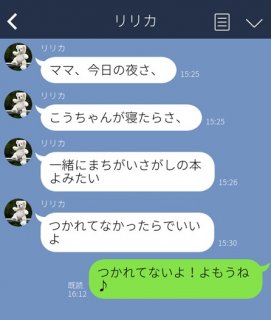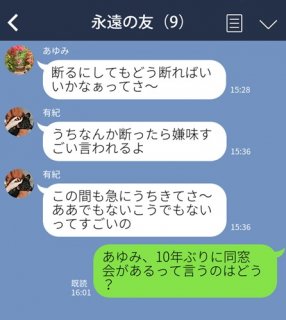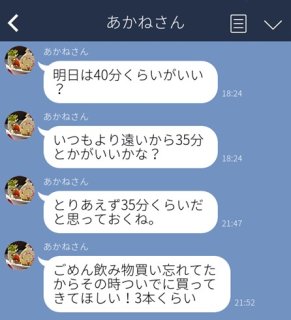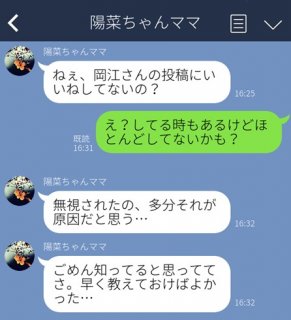すべてが、このなにもない街のためなのだ
――浜野大輝を招いて、映画を語る会、なんてどうだろうか。
思いついたら、朱里の身体が動いていた。持ち前のフットワークを生かして、すぐに彼の事務所にオファーの連絡をする。
検討しますという回答はすぐに来た。
本当は、集客のために旧知の有名人の力を借りるなんて、ちょっと恥ずかしい。つい最近まで、その活躍を知りながらも、作品には目も向けようとしなかったくせに。
クリエイター特有のものなのだろうか。朱里は、大輝をはじめとする同世代の活躍から目を背けがちだった。同じ故郷出身ならなおさらだ。自分のテリトリーの中では自分が一番でありたい、そんな気持ちが潜在的にある。
地元じゃ負け知らず。だけど、意気揚々と出て行った東京では、居場所を見つけることができなかった。
東京で存在感をみせつけた大輝なら、この焼け畑のような田舎を目覚めさせてくれるだろう――嫉妬だとか、悔しいとか、今はそんなこと、言っていられなかった。
すべてが、このなにもない街のためなのだ。
何日たっても、大輝の事務所から連絡がくることはなかった。
暇をもてあそび、店の窓から見える雄大な海をスケッチしながら、朱里はその日10回目のため息を吐く。
今日の売り上げは5000円にも満たなかった。そのわずかな金額も、妹・理子が子連れで来て飲み食いしてくれたそれだけの額だ。
「あーあ、カフェのお手伝いしたかったのに~」
理子は廃棄処分寸前のキャロットケーキの塊を小さな娘とシェアしながらつぶやいた。
「ごめんね、出番を作れなくて…軌道に乗ってきたら必ずお願いするから」
「てか、なんでギャラリーカフェなんか開いたの? 普通でいいのに」
アートやカルチャーの素養が一切ない故郷
「ええと――」
朱里は、納得させられる言葉が何も出てこなかった。理子はその沈黙を縫うように、朱里にぼやく。
「飾ってある絵もさ…有名な人のかもしれないけど、何を訴えているのかよくわかんないよ。カフェの名前も読みにくくて、モニターの映画も難しいし、この辺の人なら、TV垂れ流しで十分だよ」
さらに、反論ができない。もっともなのだ。
ライフスタイル 新着一覧




 公式X(Twitter)をフォロー
公式X(Twitter)をフォロー