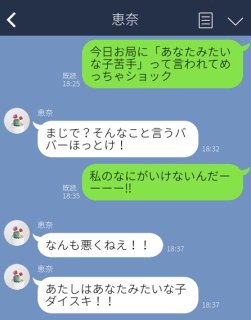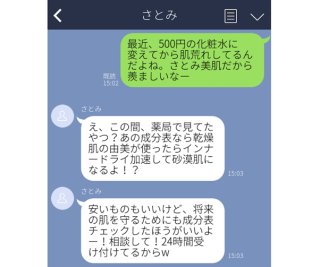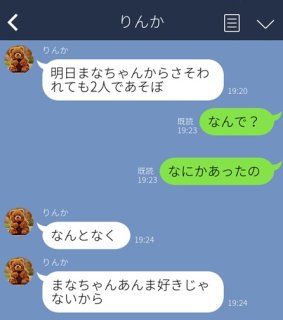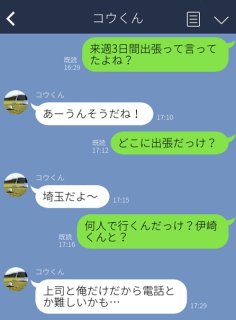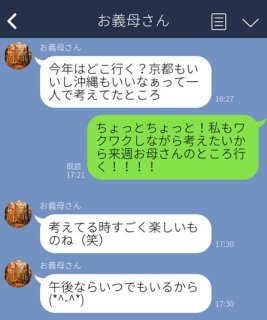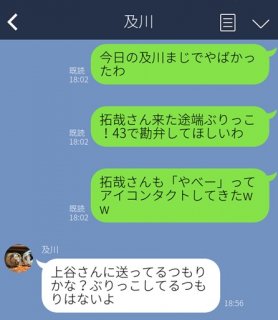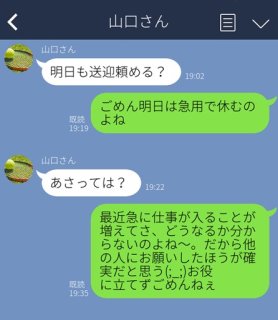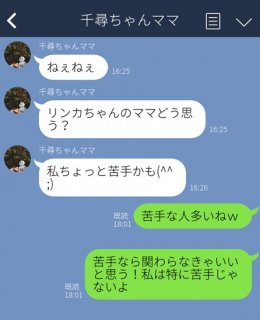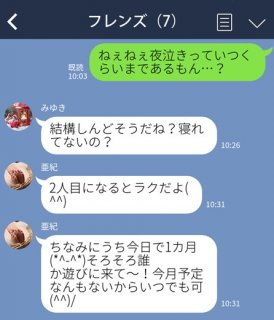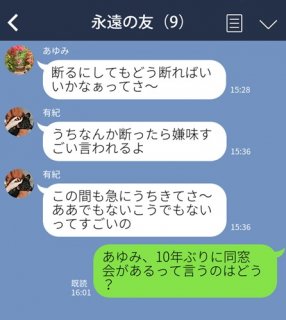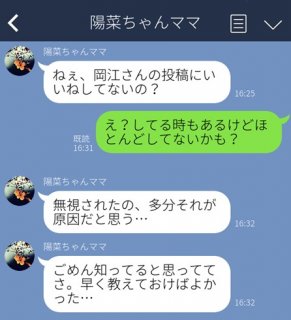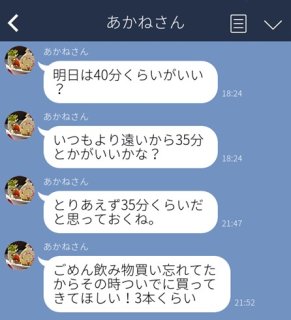ふたりきりの店内。終電が近づくけど…
ふたりきりの店内。たわいもない話で数十分。この時間がいつまでも続いて欲しいと思った。
でも、確実に終電の足音は近づいてくる。
「ちょっとお手洗い」
お手洗いはビル共有。一度外に出る必要がある。私は重い扉を開け、夜風にあたった。感情を冷やして、暴走しそうな車にブレーキをかける。
「あれ…?」
目に入ってきたのは、店の前の<CLOSED>となった看板だった。
この店は、オールナイト営業だったはず。思い返せば、あんなにひっきりなしに入店があったのに、しばらくお客さんは来ていない。
私は閉じた扉をまた開けた。
「どうした? 誰か入ってた?」
カウンターの外に出て、テーブルを拭いていた男の背中に、私は思わず身を委ねた。
ブレーキはバカになる。
上司との恋愛を思い出す。あの辞令はもしや…
薄い壁の向こうから聞こえる、恋人たちの愛し合う声で目が覚めた。
傍らには、“こと”を終えて上下する昔の男の胸元--「鍛えている」と言っていたものの、長い年月の流れを感じさせる、相応の張りと手ざわりだった。だけど、それさえも愛おしく思えた。
一晩明けても、魔法はさめていなかった。指先で彼の輪郭をなぞりながら、溶け合った記憶をたどる。
昨日の晩。すぐ店を閉めたあとは、崇がよく行くという、百軒店のバーへ。そして、いつのまにか円山町の小さな部屋へたどり着いた。
誰かと同じベッドで寝るのは5年ぶりだった。妻子ある上司と交際していた時以来だ。その上司は、今や会社の取締役である。
――あ、もしかしたら、あの辞令は……。
あの人のことだから、現場でくすぶっている私を良かれと管理職へと引き上げようとしてくれたのかもしれない。
だけど、私の中では時期尚早だ。出世と言う名の、現場からのリストラである。私はまだまだ途中の人でいたい。まだ、その先には行きたくない。
ライフスタイル 新着一覧




 公式X(Twitter)をフォロー
公式X(Twitter)をフォロー